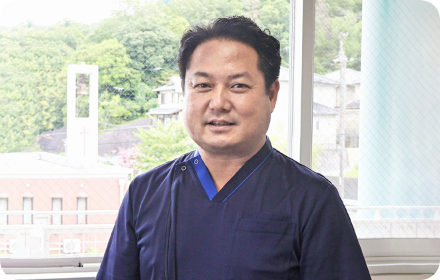本研修は、中規模病院でも現実的かつ効果的な選択肢です。各ラダーの到達レベルに沿った研修プログラムが整い、ラダー昇格と教育が連動した本格運用を実現できました。
Q1: 導入のきっかけを教えてください
当院では、2023年のリリース当初からS-QUEクリニカルラダー別研修(以下「本研修」)を導入しています。導入以前は、研修担当者がプラン立案や資料作成に多くの時間と労力を要しており、中規模病院で教育委員の人数が限られている当院には大きな負担でした。特にラダーⅢ・Ⅳの研修ではその傾向が強く、外部講師の招聘にはコストだけでなく企画や運営の手間も発生していました。こうした背景から、本研修は現実的かつ効果的な選択肢となりました。
Q2: どのように利用していますか?
当院のラダー制度では昇格基準をいくつか設けており、昇格は本人の意思による「自己申告制」です。2023年はラダー制度の改革期にあり、各ラダーの到達レベルは明確化されていたものの、それに沿った研修プログラムの整備に課題がありました。しかし本研修の導入により、これらを解消できました。
具体的には、各ラダーの能力カテゴリごとに「集合研修」と「自己学習」の枠を設け、当院に適した講義を選定しています。講義選定は自施設が強化したい分野や受講者のフィードバックを反映し、適宜修正・アップデートします。なお、自己学習項目は必須枠と選択枠に別れ、後者は自分の興味のあるものを選べるよう配慮しています。受講は自己申告制ですが、ラダー制度と教育がうまく連動し本格運用につながったと思っています。受講期間を月単位や四半期単位で区切ることで、受講履歴の確認や定期面接時のフィードバックにつなげやすくしている点も良かったと思います。
Q3: 今後の期待、展望などについてお聞かせください
現在、ラダー制度や集合研修は本研修とうまく連動していますが、これだけでは十分とはいえません。看護師が生涯にわたり学び続けることは専門職としての務めであり、「学習して良かった」「もっと学ぼう」と思える風土や仕掛けをつくることが、組織や管理者の重要な役割です。そのためには、生涯学習(個人ワーク)がスタッフ一人ひとりの主体的な取り組みとして根付くことが理想です。「学び」と「働くこと」を連動させ、学んだ内容を日々の実践(アウトプット)で生かし、その成果を実感できる環境をつくることで、学びの好循環を根付かせたいと考えています。
具体的には(まだ構想段階なのですが)、各部署の教育委員に加え、若手スタッフを研修活用推進メンバーとして選出し、実践に連動しやすい講義(鉄板講義)を選定。その資料を冊子化し、OJTやカンファレンス、振り返りに活用します。これが部署内の共通言語となり、主体的な学びの風土醸成につながると考えています。また、目標管理面談と研修講義を連動させることで、生涯学習と好循環の組織文化を実現したい、そのようなことを考えています。